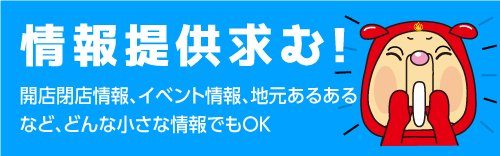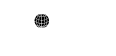【八王子市】高尾の森わくわくビレッジで体長50センチになる奥多摩やまめが育てられています
感動と発見と楽しさの「高尾の森わくわくビレッジ」で京王電鉄社員起点オープンイノベーションプログラム「My turn」の2次選考通過者が、「高付加価値な食材の安定供給で飲食店の課題を解決」をテーマに、共創による事業化を目指して実証実験を開始しています。
2025年8月4日(月)から、高尾の森わくわくビレッジの敷地を利用して、京王電鉄の共創パートナーであるアクポニが提供する「アクアポニックス」を用いて、水耕栽培と養殖を掛け合わせた循環型農業を実施中です。

わさびやクレソン、セリ、「奥多摩やまめ」などの野菜・魚を成育しているそう。
この実証実験を通して、地産地消やサステナブルなど、ストーリー性のある食材の生産と安定供給を目指しています。

写真はイメージです
「アクアポニックス」を活用した実証実験について
(1)実証実験内容
飲食店の課題を調査していく中で、ストーリー性のある食材が求められているにも関わらず、異常気象や生産者の後継者不足により安定供給できていないという課題が見えてきました。
アクアポニックスにより、環境配慮・地産地消といった付加価値を備えた食材を安定的に飲食店に提供することで、社会課題解決につながるかを検証していきます。
特に、今回の実証実験で成育予定の奥多摩やまめは、東京都水産試験場(現在は奥多摩魚養殖センター)が開発したブランド魚で、通常のヤマメは2年で成熟し、体長は約20~30㎝であるところ、奥多摩やまめは4年で約50㎝まで成長するため、刺身やムニエルなどで脂ののった上品な味わいを楽しむことができます。
(2)実証実験期間
2025年8月4日(月)~2026年1月31日(土)
※成育状況によっては、終了時期が変更となる場合があります
(3)実証実験場所
場所:高尾の森わくわくビレッジ
実証実験を行うわくわくビレッジでは、京王電鉄が「みらいにもっとわくわくを」を事業コンセプトに、高尾の自然豊富な高校跡地である施設を活かし、地域の大学や企業、生産者等の地域リソースを活かした多摩ならではの地域循環型教育を行うことを目指しています。
循環型社会やアクアポニックスの仕組みを展示するほか、今回の実証実験により収穫される野菜をイベントで活用するなど、子どもたちに循環型農業を体験・学習する機会を提供しています。

京王社員起点オープンイノベーションプログラム「My turn」について
(1)概 要
株式会社ユニッジの支援のもと、京王電鉄社員の思いやアイデアを起点に、外部企業との共創により新規事業を創造するオープンイノベーションプログラムです。2024年7月から開始し、255件の書類審査の中から、書類審査、一次審査会を通過した11件の事業化アイデアについてプロトタイピング検証、共創パートナーの募集、選定を行いました。その後、6月18日(水)に実施した審査会にて6件の採択案件と共創パートナーが決定し、7月以降順次実証実験を行っていきます。2026年1月に予定をしている最終審査会にて、事業化案件を決定します。
「アクアポニックス」の概要
「アクアポニックス」は、水耕栽培と養殖を掛け合わせた次世代の持続可能な循環型農業であり、魚の排泄物を微生物が分解し、植物がそれを栄養として吸収、浄化された水が再び魚の水槽へと戻る、生産性と環境配慮の両立ができる生産システムです。また、アクアポニックスはエネルギー・資源循環効率の向上、持続可能な大規模食糧生産とグリーン化、スマート農業の推進、循環型の複合的ビジネス展開などにも寄与します。
このシステムでは、魚などの水生生物への影響を配慮し農薬や化学肥料・除草剤を使用しないため、環境負荷を軽減しながら安心安全な野菜を生産することができます。そのため、生産された野菜は硝酸態窒素含有量が少なく、生でも食べやすいとされています。
高尾の森わくわくビレッジについて
東京都のPFI事業により運営されている、都立八王子高陵高校の建物を再利用して作られた、宿泊可能な体験型学習施設です。緑豊かな環境の中、人々が自然とふれあいながら家庭や学校では体験できない学びの喜びを発見できる場を目指しています。家族での宿泊や学校・クラブの合宿、企業研修、スポーツ、キャンプなど、子どもから大人まで全ての方が利用できます。地域に密着してきた京王グループと、青少年社会教育に貢献してきた東京YMCAグループが、ノウハウを活かし 総力をあげて運営に取り組んでいます。
高尾の森わくわくビレッジはここ↓
記事協力:京王電鉄